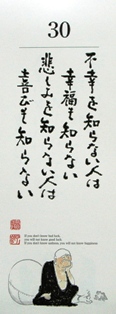■今年も「みたままつり」
毎年、私は靖国神社の「みたままつり」に行っているので、今年も行った。私の父母やその兄弟で戦死した者は1人だけだが、その人を私は知らない。
なぜ行くかと言うと、我が家から近いし大量に奉納された提灯の写真を撮るためである。森下駅近くで家族と夕食を食べてから、そこで2人と別れて地下鉄新宿線で私だけ靖国神社に向かう。

「靖国問題」に触れるのはこのサイトでは相応しくないので、私の意見は書かない。ただ日本人なら色々な意見はあると思うが、みんな一度はここへ行ってみた方が良いとは思っている。
靖国神社には「遊就館」という戦争記念館がある。
以前は「なぜ遊という字と就職の就という字が付いているのかなー?」と思っていた。

これを調べたら、中国の古典である「荀子」の中にある「君子は居るに必ず郷をえらび、遊ぶに必ず士に就く」から来ていた。
この意味も調べた。「居るならば、自分の居るべき場所を選び、学ぶなら自分にとってより良き先生に就きなさい」という意味だそうだ。

遊就館の左前にはパール博士の顕彰碑がある。
パール博士とは本名をラダ・ビノード・パールといい、インド人の国際法学者である。
彼は東京裁判でただ1人この裁判を「勝者による儀式化された復讐」と断じた。パール判事の意見書はGHQが発表を禁じたという歴史が、この顕彰碑を見ると分かる。

地下鉄「九段下駅」を出ると、もう靖国神社に向かう人の波がある。
大鳥居をくぐると、両側に大量の奉納された提灯が神門まで続く。
辺りが暗くなると提灯に灯がともり、これがなんとも良い雰囲気を出している。神門には巨大な七夕飾りが下がっていて、これを内側から撮る写真が良い感じとなる。

大鳥居をくぐり参道を進んで行くと、丁度、神輿が神門に向って練っているところに出会った。参道は大混雑だが、多くは参拝者ではなく、お祭りを楽しむために来ているように感じる。
それは若者と外国人が多く、靖国神社に縁のあるような年配者の姿があまり見えないことから分る。
「みたままつり」はドンドンと観光化されていて、本来の先祖の霊を祀るという意味が薄れている。
風紀が乱れ屋台が禁止されていた2年前までは、静かな本来の「みたままつり」で良かったのになー。

神門を入り拝殿に向かう。
ところが、人出はあるのに参拝者はわずかだ。
今年は靖国神社の創立150年となり、例年よりかなり参拝者が多いと思っていたのだが・・・。
お金のことを書くのは憚られるが、大型提灯の献灯は1万2000円、小型でも3000円であるから3万灯では幾らになるか?、下品になるので、計算はしない。
人が多く疲れてしまったので、早々に写真だけ撮って家に戻った。

(おまけの話)
10年以上も前のことだが、拝殿の奥にある本殿に上がって正式参拝したことがある。
ここに上がるには右手の参集殿で申し込みをする必要がある。
その時に申込用紙に住所・氏名などの連絡先を書き、玉串料として、最低でも3000円を収める必要がある。

一定の人数が集まると、神主に先導されて拝殿に向かう。
そこで少し待たされる。この時に後ろを振り返ると、一般の参拝の人達が私を拝んでいるように見えるのが可笑しい。
次に本殿に案内されて、正式に参拝となる。
神主の指示に従い儀式は終り、お供物を頂いて戻るのである。

なんでも簡素化された現代に、「正式」というのは大事である。
「正式」を止めてしまうと、綿々と続いて来た日本の伝統も令和の時代で消え去ってしまう。
「なんでも日本が良い」とは思わないが、「日本の良き伝統は残したい」。それが日本人の私のアイデンティティもあるからだ。


 2月の山中湖
2月の山中湖  丸ビル方面の夜景
丸ビル方面の夜景  ラーちゃん
ラーちゃん
 隅田川
隅田川  東京スカイツリー
東京スカイツリー