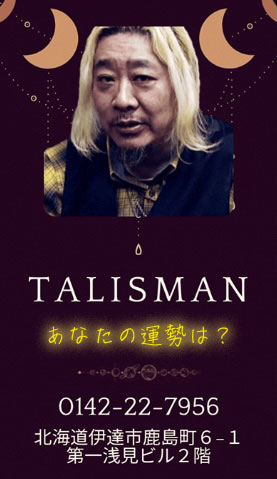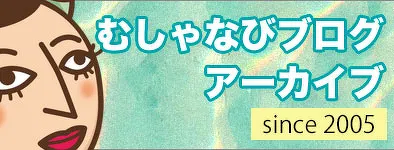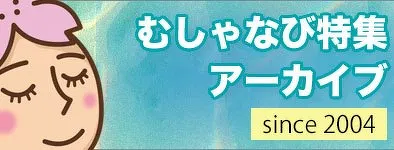ホテルマンの幸せ
Post Index
記事一覧
ただいま準備中です。
Tag
ハッシュタグ
Archive
月別アーカイブ
「むしゃなび」はこちらの皆様に支援して頂いています
Popular Post
人気の記事
-

06/26(木) あの日を振り返って…
-

06/27(金) 気のせいであっておくれ…
-

06/25(水) 興味がある植物について
-

06/30(月) 果てしなく遠い甲子園への道
スポンサーリンク
-

06/25(土) - 広告
四季を通じ、「外」とつながる暮らしの提案
ダイニングに向かう動線の視線の先にも、光の漏れる地窓。
Event
イベント
「」カテゴリーのおすすめ記事
-
ホテルマンの幸せ

0
-

2025/02/11(火) 今日のメインは牛肉の赤ワイン煮込みです!
観月旅館

0
-

2025/04/29(火) 死ぬとき心はどうなるのか?
心の伊達市民 第一号

0
1
-

2025/06/14(土) いよいよ明日になりました☆
ホテルマンの幸せ

0
-
ホテルマンの幸せ

0
Popular Blog
人気のブログ