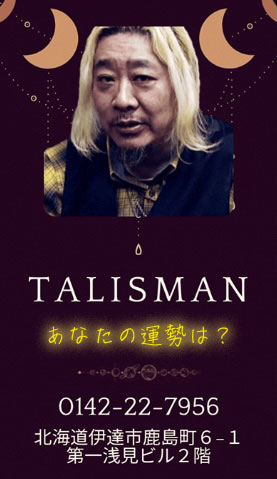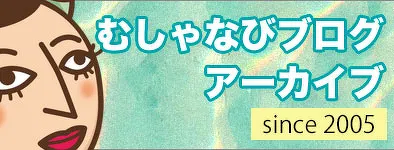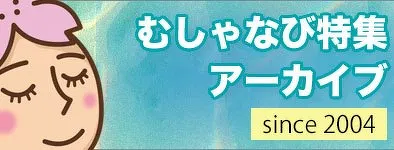観光・体験
観光・体験 記事一覧
-

心の伊達市民 第一号

0
2
-

-

心の伊達市民 第一号

0
2
-

心の伊達市民 第一号

0
2
-

心の伊達市民 第一号

0
1
-

心の伊達市民 第一号

0
1
-

ホテルマンの幸せ

0
-

-

心の伊達市民 第一号

0
2
-

心の伊達市民 第一号

0
1
-

-

心の伊達市民 第一号

0
1
-

-

ホテルマンの幸せ

0
-

心の伊達市民 第一号

0
1
-

心の伊達市民 第一号

0
2
-

-

心の伊達市民 第一号

0
2
-

心の伊達市民 第一号

0
2
-

心の伊達市民 第一号

0
1
-

-

心の伊達市民 第一号

0
2
-

心の伊達市民 第一号

0
2
-

-

-

心の伊達市民 第一号

0
2
-

心の伊達市民 第一号

0
1
-

心の伊達市民 第一号

0
2
-

-

心の伊達市民 第一号

0
2
-

心の伊達市民 第一号

0
2
-

心の伊達市民 第一号

0
2
-

-

心の伊達市民 第一号

0
2
-

心の伊達市民 第一号

0
2
-

ホテルマンの幸せ

0
-

心の伊達市民 第一号

0
1
-

心の伊達市民 第一号

0
1
-

ホテルマンの幸せ

0
-

心の伊達市民 第一号

0
2
-

心の伊達市民 第一号

0
2
-

-

心の伊達市民 第一号

0
2
-

心の伊達市民 第一号

0
2
-

-

心の伊達市民 第一号

0
2
-

心の伊達市民 第一号

0
1
-

-

心の伊達市民 第一号

0
1
-

心の伊達市民 第一号

0
1
-

心の伊達市民 第一号

0
1
-

心の伊達市民 第一号

0
2
-

心の伊達市民 第一号

0
2
-

ホテルマンの幸せ

0
-

-

心の伊達市民 第一号

0
1
-

心の伊達市民 第一号

0
1
-

ハッシュタグ
- お肉(275件)
- ボリューム(233件)
- お袋の味(102件)
- あったかメニュー(84件)
- 豚肉(67件)
- 国産(61件)
- カレーライス(55件)
- 北海道産(50件)
- 鶏もも肉(50件)
- 豚ロース肉(46件)
- あっさり(42件)
- 挽肉料理(40件)
- 煮込み料理(38件)
- あんかけ焼きそば(33件)
- 伊達産(31件)
- 豚バラ肉(31件)
- フライ料理(28件)
- 肉肉しい(27件)
- 唐揚げ(26件)
- 和食(25件)
- 中華料理(24件)
- 思い出作り(23件)
- 豚カツ(22件)
- ハンバーグ(21件)
- 手づくり(20件)
- カレー(19件)
- キッズフォト(19件)
- 生姜焼き(19件)
- 豚肩ロース(18件)
- 野菜たっぷり(18件)
- 豪華(17件)
- #洞爺湖(17件)
- 海外の話題(16件)
- 定番メニュー(16件)
- 家族フォト(16件)
- 豚バラ肉のおかず(16件)
- かつとじ(15件)
- 753フォト(15件)
- 豚汁(15件)
- ユーリンチー(14件)
月別アーカイブ
スポンサーリンク
-

06/25(土) - 広告
四季を通じ、「外」とつながる暮らしの提案
ダイニングに向かう動線の視線の先にも、光の漏れる地窓。
観光・体験 人気の記事
-

06/24(火) 写真で見る東京(109)・・・六本木から東京タワー
-

06/25(水) 写真で見る東京(110)・・・銀座のガス灯
-

06/23(月) 写真で見る東京(108)・・・両国界隈
-

04/03(木) 「ニコン ミュージアム」に行く
-

01/31(金) NHK放送博物館と愛宕神社
-

06/19(木) 「山王祭」と「つきじ獅子祭」
「観光・体験」カテゴリーのおすすめ記事
-

2025/01/31(金) NHK放送博物館と愛宕神社
心の伊達市民 第一号

0
2
-

2025/06/24(火) 写真で見る東京(109)・・・六本木から東京タワー
心の伊達市民 第一号

0
2
-

2025/04/15(火) 写真で見る東京(89)・・・六本木の桜
心の伊達市民 第一号

0
2
-
心の伊達市民 第一号

0
2
-

2025/05/19(月) 神田明神の「神田祭」
心の伊達市民 第一号

0
1
観光・体験に関する
特集記事
-

『自然と科学のミュージアム「森の工舎」』 〜自然と人への愛を感じる癒しと学びの時間
2Fから吹き抜け越しに1Fのフロアを覗くと見えるこのソファ(?) 何をモチーフにしているのかお分かりでしょうか? 時間が経つのを忘れてしまう。 白老虎杖浜にある『ナチュの森』は、1日中居られる… いえ、1日では足りないと感じる心地よく学びの多いところでした。 今回は『ナチュの森』の中に2022年12月OPENされた「森の工舎」の取材で訪れたのですが、 ナチュの森の全てを案内していただきました。 丁寧な案内をしてくださったのが、「ナチュの森」広報担当の 山本祥史さんです。 さて。 皆様、いろいろな名前が出ているので、そろそろ混乱し始めていらっしゃいますよね…。 そこでちょっと、「ナチュの森」のこれまでの歩みと背景について簡単にご説明しますね。 ナチュの森の運営会社は東京本社の株式会社 ナチュラルサイエンスという名の低刺激スキンケア商品メーカーと北海道本社の株式会社 ナチュラルアイランドという名の北海道素材に着目したスキンケアメーカー 2011年 白老虎杖浜の工業団地用地を取得 2014年 地域説明会、協議会などを経て、閉校した旧虎杖中学校(1988年使用開始の校舎)土地建物売買契約を締結 2017年 ナチュラルアイランドの北海道工場竣工 2018年 ナチュの森オープン 2022年 自然と科学のミュージアム「森の工舎」オープン “ 校舎 ” が ” 工舎 ” に生まれ変わった時でした。 このような歩みを経て、虎杖中学廃校跡地を活用した工場&ガーデン施設「スキンケア工園 ナチュの森」は完成しました。 ただ、このように箇条書きにしてしまうと、その道は淡々と着々と進めてこられたように見えます。 けれども、「北海道の自然の恵みを素材にした商品作りをしたい」という構想から15年、 この地に出会ってから完成まで10年が経過しました。 このプロジェクトに向けられた大きな原動力は、自然と人への大きな愛でした。 それを実感できるのがこちら。 こちらの冊子は「ナチュラルアイランド」のものです。 表紙の花は、皮膚のガードマンとも呼ばれる万能ハーブのカレンデュラ。 ナチュラルアイランドのカレンデュラ製品は、全てナチュの森のファームで栽培された花を使っているそうです。 この冊子、「ナチュの森」を訪れた時、ぜひ開いて見ていただきたいです! 筆者は全26ページの冊子を美しい写真とともに読み終えた時、 胸が熱くなり幸せな気持ちになりました。 今やどこでも溢れている言葉。 「持続可能な」や「環境にやさしい」という文字はこの中のどこにもありません。 読み進めながら感じるのは、 「大切なものは敬意をもって守る」という自然へのリスペクトと人へのリスペクトでした。 さて、それではいよいよ今回の主役的な建物、 旧虎杖中学校校舎「森の工舎」のお話に入ります。 と、その前に。 実は〜 アポイントメントの時刻は13:00でした。 私が到着したのは10:00。 山本さんにお会いする前にどうしても体験したかったのがこちら。 「蒸留カフェ」も魅力的でした。 「花のある暮らし」〜エッセンシャルオイルを楽しめるドライフラワーアレンジ ワークショップ(こちらは2/28までの期間限定メニューです) 季節ごとにワークショップメニューが変わります♡ ワークショップが行われるスペースは「森の工舎」の無料スペースです。 このスペースには、「蒸留カフェ」と「ショップ」があります。 取材前のランチには、スパイシーでお肉ごろごろなカレーセットをいただきました。 この前に、蒸留した高知産生姜エキスを使った甘味ゼロのジンジャーエールもいただきました。 スッキリ爽やか!初めての味でした。 ママと赤ちゃんが一緒に使える、「ナチュラルサイエンス」看板商品の低刺激スキンケア製品も販売されています。 これすごい! 他の商品を知りません! 皆様、俱多楽湖や虎杖浜の語源をご存知ですか? どちらも「イタドリが生えるところ」を意味しているのです。 まさにここならではの商品です。 さて、それでは本題。 そもそも何故、「ナチュラルサイエンス」は北海道白老町の虎杖浜に『ナチュの森』『森の工舎』を作ったのでしょうか? 「弊社が北海道の豊かな自然の恵みで化粧品を作りたいと考え、 低刺激化粧品にとっての最も大切な原料である「水」を探し求めていたときに、 ようやく巡り会えたのが白老町に位置する倶多楽湖の湧水(カムイワッカ=神の水)でした。 それは、他の素材を最大限に活かせる肌に優しい軟水でした。 そして、湧水口の近くには既に閉校になることが決まっていた虎杖中学校がありました。 その中学校を見学させていただき大変驚きました。 校舎は古いのに、とても掃除が行き届いていて落書きひとつありませんでした。 ずっとずっと大切に綺麗に使われてきたことがすぐにわかりました。 そのとき、『この建物と、これまでの生徒さんたちや先生たちの想いを 「ナチュラルサイエンス」で引き継いでいきたい!』と強く思ったのです。 本当は水を探して北海道中走り回っていたので、 物件探しをしていたのではありませんでした。 ですが、その時そう思ったのです。 そして、「虎杖中学校の跡地に湧水を引き込んで工場を作れないか」「校舎や体育館は取り壊さずに、そのまま残して再利用できないか」と考えるようになりました。」 なるほど…、それが「ナチュの森」が生まれるきっかけだったのですね!ちなみに「校舎」が「自然と科学のミュージアム 森の工舎」になったのは何故ですか? 「はい。ナチュラルサイエンス・ナチュラルアイランド」の工場と「ナチュの森」を運営している中で、この校舎を活用し、周辺地域の自然の恵みを利用させていただき、地域に貢献できることは何かを探っていった結果の形が、私たちが大切にしている「ものづくり」を体感する「自然と科学を通して物事を体験する」場としての「森の工舎」となりました。 また、とても重要なこととして、自然の恵みを得るためにはそのままでは毒になることもあるということがあります。 大学や研究機関との連携の中で判明した研究結果の共有も、ここを通して行いたいという考えもありました。」 訪れた時、「蒸留実験室」では、ちょうどタイミングよく釧路産モミ(トド松)の蒸留を行っていました。 使われる水はもちろん俱多楽湖のカムイワッカ。 フラワーアレンジメントを途中にして飛んで見に行った筆者です。 仕込んでから40分ほどでエッセンシャルウォーターが採れます。 先ほどのドライフラワーアレンジメントには、好きなエッセンシャルオイルが付いていました。 実は私、この後のお話を知らずにこの和ハッカのものを選ばせていただいていました。 和ハッカの貴重品種「JM-23」を、滝上町の農家 瀬川さんは2haの広さの畑で大切に育てています。 世界で唯一、瀬川さんだけが栽培されている和ハッカはとても貴重です! また、この実験室では、四季に合わせた様々な植物を使った体験会なども行われます。 この日はラベンダーサシェ作りの準備がされていました。 「アトリエ」では、お子様向けの自然と科学をテーマにしたモノづくりを体験できます。 「香りのラボ」には調香室も備え、様々な香りを体験しながら、今の自分に合う香りを分析する体験ができます。 そして「ライブラリー」では数千冊の本が並びます。 とにかく選書が素敵すぎです! ネイチャー関連の本もたくさんあります。 なんと、なかなか見ることがない貴重な本まで!! ホント、びっくり!! どんな本があるのかは、ぜひ実際に訪れて見つけてみてくださいね☆☆ 読書のための椅子の配置も心地よい。 ここだけで1日いられます。 そして。 なんて素敵な〜!! と思ったのがこの空間♡ 元々は半円形だった天井を丸く整え、太陽をモチーフにした大きな照明をつけました。 灯りの点き方にも工夫が施されています。 そしてその下の吹き抜けのところには蛍光灯をリサイクルして作られたガラス照明「ウォーターバルーン」が、雨粒の如く各色ゆらゆらと煌めきます。 そしてその下には…。 そう、記事の最初に登場した丸いソファは俱多楽湖をイメージしたものでした。 そのソファーに寝転べば、こんな空が広がっていました。 太陽 雨 湖 それらの循環が表現されています。 そしてもっと素敵だったのがこちら〜 この日ちょうど、こちらのライブラリーで、旧虎杖中学校の卒業生の皆様と出会いました。 実は、山本さんのお隣にいらっしゃる女性は、虎杖中学校出身で現在は「ナチュの森」の工場の従業員の方でした。 そして、さらに左側の男性お二人も「ナチュの森」の従業員の方々でした。 こちらで働く従業員さんは、9割の方が地元採用だそうです。 だから、こちらの3名の方々の他にも、たくさんの卒業生がこちらで働いていらっしゃるはずです。 かつて、ここで学んだ生徒だった方々が、今度は働く場としてここに戻ってきている。 これもまた、素晴らしい循環です。 地域との関係の良さが窺えます。 学校ではなくなった今も、 こうして卒業生が気軽にこられる雰囲気作りをされていることに感動! あまりにも感動して、写真を撮らせていただきました♡ 「えほんの部屋」もあります。 0歳からのお子様と保護者の方のための部屋です。 ナチュラルカラーのマットを階段上に配置した向かい側には〜 人形劇などが上演できる舞台があります。 こちらでは今後、紙芝居などいろいろなイベントを開催するそうです。 「ギャラリー」では、北海道初上陸の「ようこそ絵本のまちへ展」を開催中です。 もと体育館だった「あそびのひろば」は、全天候型のあそび場になっています。 白老町の登別寄り、虎杖浜温泉から山の方に入ったところにある俱多楽湖のカムイワッカを引く親水公園の隣。 この水に惚れ込んだ会社「ナチュラルサイエンス・ナチュラルアイランランド」の建物が現れます。 ・自然の恵みを安全に大切に享受するために、自然を科学すること。 ・地域の人々の故郷への想いを大切にすること。 ・地域の人々と仲良くして、地域の役に立つこと。 これらを信条に、「森の工舎」は今後も進化していくことと思います。 朝から訪れたというのに、外に出ると薄暗くなっていました。 「森の工舎」は、時間を忘れて過ごせるところでした。 ―ナチュの森 森の工舎 情報― ナチュの森HP https://nachunomori.jp 森の工舎 https://nachunomori.jp/morinokousha_pre ナチュの森 Instagram https://instagram.com/nachunomori_official?igshid=YmMyMTA2M2Y= ナチュラルサイエンス Instagram https://instagram.com/naturalscience.official?igshid=YmMyMTA2M2Y= ナチュラルアイランド Instagram https://instagram.com/naturalisland_official?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Rietty

0
-

-

-

きのこから森を観て、森から地球を観る 〜愛ある きのこアドバイザー 中嶋潔ワールドへようこそ!
きのこ観察会にて この日は、倶知安にある「GURUGULU」というオフグリットのゲストハウスで「きのこ観察会」が行われました。 参加者は小さなお子様から大人までの15~6人。 この日筆者は、「きのこ観察会」への参加と、今回の主人公 中嶋潔氏 の取材目的で出かけて行きました。 お天気最高の野外活動日和♪ 実は筆者、潔さんの観察会には“きのこ”以外でも参加しています。 今回で4回目。 中嶋潔ワールドは、毎回飽きることなく楽しい時間を過ごせます。 何故かって? それはきっと、森愛溢れる潔さんと森にいると、とても楽しくて、平和で、幸福感が何倍にもなるから。 森がいっぱいの日本に住んでいて良かった! 地球に生まれて良かった! そんな幸せの時間を与えてくれる人だからです。 子どもも大人も惹きつける潔さんの技はひとえにお人柄が成すものです。 子どもって、そういうところを察する力に長けていますので、すぐに人気者になってしまいます。 中には、きのこ博士くん候補生のように詳しい子もいました。 毎回観察会を楽しみにしているご家族もいらっしゃるようです。 そして観察会の締めは約11種類もの“きのこ”が入ったうどんを毎回振る舞ってくれます。 実は皆、これも大の楽しみ🎶 林床への興味 実は潔さんは、あの難関資格「森林インストラクター」でもあり、「きのこアドバイザー」でもある森の人。 2001年から6年間林業に携わり、現在はニセコのリゾート会社にお勤めです。 「北大のポプラ並木が倒れたり、支笏湖周辺の森の木が軒並みなぎ倒された大きな台風が来た2004年、悲しいことにリストラに遭ってしまいました。管理する木がほとんど倒れて無くなってしまったからです。でも林業の仕事が大好きだったのでその後は民間会社の林業部門で働きました。林業に携わっていた6年間で行っていたのは、育苗・植林・伐採・管理。おもにトドマツ・アカエゾマツ・カラマツ・ミズナラ・ケヤマハンノキなどを植えていました。働き始めた頃は何も知らなかった樹木の名前も、毎日触れて観察をしているうちに、2年で倶知安周辺の樹木は全て覚えてしまいました。この地域の樹木について、ある程度把握できてきた時に、次に興味が湧いたのが、いつも樹木のそばの地面にいる、きのこたちでした。」 「興味を持ち始めた頃から直ぐに“きのこ観察会”を催すようになりました。自分自身はまだまだよくわからなかったので、黙々と独学もしつつ、『誰か詳しい人!?』と呼びかけて興味がある人や詳しい人と一緒に観察をすることで少しずつ覚えていきました。最初の頃は図鑑を森に持って行き、調べながら歩いていました。でもそれをやるとなかなか進まず多くを観察できません。実は、“きのこ”ってまだ良く分かっていないことが多いです。日本には5千〜1万種類くらいはあると言われていますが、その内、名前が付いているのは2500種類くらいです。そしてそれらのうち、一般的な図鑑に掲載されているものが800種類ほどです。名前のない不明菌と呼ばれるものの方が非常に多いことになります。実際に森を歩いていてもわからないものがたくさんあるわけです。だから、図鑑を持ち歩くのはとても非効率になります。ある日、北海道大学名誉教授の五十嵐教授の観察会の仕方を見て衝撃を受けました。森の中では一切図鑑を開かなかったのです。だから、僕も現場で図鑑を開かずに、種を言い当てることができるようになる努力をしました。きのこ用のカメラを買い、色々な角度から写真に収めてあとで調べるという方法をとりました。10年くらい続けてやっと種の見分けに信憑性が出てきたかな〜。」 にわか仕込みで覚えようとしている筆者には耳が痛い話です^^; 「また、FaceBookでは『北海道のきのこ好き』というグループを作って、常に新鮮な情報交換をしています。オンライン上の趣味のグループって、とかくイザコザが起きやすいのですが、このグループは居心地の良いグループにしたかったので、しっかりルールを守り、ネット上のマナーをわかってくれる人のみを承認するようにしています。自分がなかなか見られない“きのこ”も皆さんがシェアしてくれるのでとても勉強になります。」 常に学ぶ姿勢を止めない潔さんです、 そしてじきに、潔さんに転機がやってきます。 「ニセコのある会社から、スキー場ゴンドラの夏季営業を始めるに際し、山頂で自然体験部門を立ち上げるのでその担当者にならないかという話しが舞い込みました。好きな分野でしたので直ぐにお引き受けし、2007年から2020年に廃止されるまで担当しました。コロナ禍がきっかけでその部門はなくなってしまい、今は別のセクションにいるのですがあれは楽しい仕事でした。」 今ももちろん“きのこ”への愛は変わらず持ち続け、観察会活動はライフワークとして続けているというわけです。 「ところで、“きのこ”は確かに可愛くて面白いですが、それほどまでにのめり込んだのは何故ですか?どこにそんな魅力を感じたのでしょうか?」 「石炭期を終わらせたのは“きのこ”だという話を知っていますか?」 「え? あ…はい。一応ネイチャーガイドの端くれですので…」 「“きのこ”への興味は食べられるor食べられないだけではありません。まず、一期一会で神出鬼没なところが面白いのです。“きのこ”への興味を覚えてから20年超えてもまだまだ情報は更新し続けています。実に奥が深い。地球上の“きのこ”の登場は、酸素と二酸化炭素濃度のバランスに関係しています。地球上にきのこが登場する前、植物たちは枯れても分解されることがないので、その遺骸は地面に溜まり続け、それが石炭となって地面の中に二酸化炭素の多くを封じ込めてしまいました。そのため地球の酸素濃度はどんどん上がり続けましたが、“きのこ”を含む菌類の登場により、死んだ樹木を菌類が分解するようになり、石炭はできなくなってしまいました。その後、大気は現状の酸素濃度で安定し、土壌も変化し生き物は進化し、現生の植物が誕生しました。“きのこ”の登場は、地球上の生物や植物にとってとても大きな出来事だったのです。“きのこ”をはじめとした菌類が地球上の生命活動の重要な鍵を握っているわけです。」 なるほど〜。 もうかなり前のめりな筆者。 目がキラキラしているのを自覚しました。 もっともっとその続きを聴きたい衝動を堪えて、取材モードに戻しました。 同時にここで、潔さんが一体どんな子ども時代、青年時代を過ごしたのかということに俄然興味が湧いてきました。 潔氏 小学生〜大学生の頃 「小学生の頃は物知り博士的キャラでした笑」 「それって今と変わらないですね笑」 「そうだね。たぶん僕は父親の影響をかなり受けていると思います。父は兵庫県赤穂市生まれで海育ちだったので、海が大好きな人でした。よく釣りやキャンプへ行ったなあ。今でいうグランピングのようなキャンプも体験させてくれました。父自作の2段ベッドがテントの中にあったんです。自然の中での過ごし方の基本を習ったのは父からでした。そして、ものすごい読書家で聡明でした。物事を科学的に考えることがとても好きな人で、それを試してみるのも好きでした。手先もとても器用だったので、周りが驚くようなものを色々作っていたなあ〜笑」 お父様のことを楽しそうに話す潔さん。 “ 困った人” “ 変な人 ” という言葉が何回も出てきましたが、その言葉の裏にある尊敬と愛が込められていることも筆者には伝わっていました。 「例えばね、自宅の一角にコンクリートの建物を作って、屋上に畑を作ったこともありました。ところが階段がない。梯子で上るわけです。そして父親だけはトイレを使わず糞尿を肥料として屋上の畑に撒くわけです。周りは住宅街。当然臭う。当時、父はEM菌関連の本を読み漁って研究をしました。決して環境問題に傾倒していたというわけではなく、素朴な感情で超循環の暮らしをしたいと考え、自給自足を目指していたのだと思います。大変だったのはお袋だろうなあ〜笑」 「あ。こんなこともありました。当時大阪府に住んでいたのですが、自宅の近くに天の川という名の川が流れていて、その河川付近に遊んでいる土地があると放っておけない。開墾しちゃうんですね。特に迷惑を被る人はいないとは思いますが、まあ、今なら問題になりそうですよね…^^; とにかく、学校では学べない自由な世界があることを父が教えてくれました。」 お父様のお話を伺っていたのですが、途中から潔さん自身のお話を聴いている錯覚を起こすほど、お父様の影響を強く受けていらっしゃるなあと感じて、心の中でクスッとしてしまいました。 「中学生の頃は自転車少年でした。自転車の旅が好きで、高校の卒業記念に友達と13泊14日四国の野営旅をしたこともありました。高校時代はワンゲル部・新聞部・クイズ同好会を掛け持ちしていました。自然の中にいることも、ものを読んだり書いたりすることも当時から好きでした。北海道新聞のコラムを12年間連載したこともあります。」 しまった…。 またやってしまった…。 最近どうもうっかりとモノを書く人を取材相手に選んでしまいます。 潔さんは常に笑いながら話してくれるのですが、緊張が走った瞬間でした ^^; 「大学時代はワンゲル部一筋でした。山は本当に好きで、仏教系の大学で哲学を学んでいたのですが、卒業後は北アルプスの山小屋で夏から秋まで五年間、小屋番をしていました。」 小学生から大学生時代のお話を聴き終わり、目の前にいる潔さんを作り上げてきた道筋が見えた気がしてものすごく腑に落ちました。 キノコから森を観つづけた潔さんが成し遂げたい想いとは 「最後に、成し遂げたい想いがあったら教えていただけますか?」 筆者が投げかけた質問に、それまで、ニコニコと顔いっぱいの笑顔で話していた潔さんの顔つきが急に変わりました。 「キノコは森を観る窓だと思っています。」 そう切り出した話の続きはこうでした。 「北海道の70%は森林と言われています。ずっと森を観てきた人間として、キノコを通して北海道だからこその森の守り方・育て方・稼ぎ方などを仕組み化していきたいと考えています。ご存じですか?北海道の人工林の約50%はトドマツ林です。 そしてなんと、トドマツ林にはおそらく世界で一番キノコの種類が多く生えているのです。 しかも、トドマツ林は保護林の中には存在しない。つまり、林床の利用は自由です。 北海道にしかできない「トドマツ林限定のきのこの資格制度」を作りたいと考えています。その資格制度を作ることで、北海道の人工林に最も多いトドマツ林に生えるキノコを熟知している人を増やせば、世界で最もキノコを理解している人を増やすことになります。キノコの理解者を増やすことで、森は森のまま木々を適正に管理して守り・育てることができます。木を切って売る林業ではなく、林床のキノコを売って稼ぐ林業を成り立たせる仕組み作りをしたい。トドマツの林床に生えるキノコの中には、マツタケよりも高値で取引されるものもあるんです。そして、その仕組みを推進する立場として『トドマツ林限定のきのこマイスター』が存在する。人工林ってね、人里に近いところにあるわけです。しかも人工林には必ず林道があるし、トドマツ林には笹がない。それらもその新しい仕組み作りにはメリットになります。つまり、人が入りやすくキノコが生えやすい環境である宝の森と言えるわけです。つまり、何をやりたいのかをもう一度と言うと、”森は森のまま維持する林業”の仕組み作りのために「トドマツ林限定のきのこの資格制度」を作りたい!と考えているんです。」 土の中や倒れた木の中で、人間の目には触れない世界の中に無数に張り巡らされている菌糸たちのネットワーク。 そして、空気中に飛び出した見えない胞子たち。 地表の循環の立て役者キノコたちを通して語る潔ワールドの森愛・地球愛・人間愛にすっかり魅了され、潔さんの成し遂げたい想いを応援したくなった筆者でした。 ―中嶋 潔氏 情報― FB : https://www.facebook.com/kiyoshi.nakashima.18 FB : 「北海道のきのこ好き」 ・倶知安「風土館」にて時々講演をしています。 ・「北海道のきのこ好き」に参加すると、各種ワークショップ情報を得られます。 10/29にも倶知安「GURUGURU」にてキノコ観察会があります。
Rietty

0
-