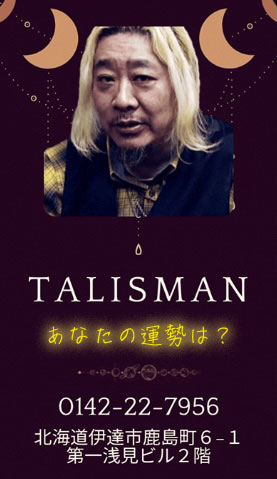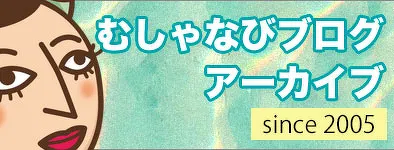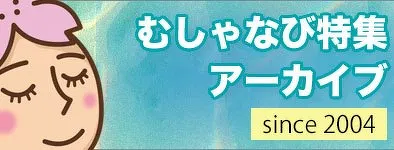娯楽・趣味
観光・体験 記事一覧
-

2025/07/11(金) - 観光・体験
- NEW
小さな話(29)
【NO LITTER】 銀座から新橋までは歩いても15分くらいなので、私はよく歩く。 表通りより裏通りの方が面白いものに出会えるので、そちらを行くことが多い。 新橋一丁目で「NO LITTER」と、英語だけで書かれた「注意書き」が見えた。 その上のマークを見ると、ここはどうも東京電力のなにか物入のドアのようだ。 落書きがあるが注意書きに日本語が無いので、「落書き禁止」と勘違いするかもしれない。でもこれは「ポイ捨て禁止」である。なぜ英語だけなんだろう? 「人種差別だ!」と言われないか? 【バーミューダパンツ】 少し前にGUCCIギャラリーで横尾忠則の絵画展があり、LINE指定の予約方法だった。 それを見に行ってしばらくしたら、広告のメールがLINEに着信した。 内容はメンズのシューズ、パンツ、バッグなどの新製品の紹介だった。 試しに見て驚いた。コットンのバーミューダパンツが、なんと15万9500円だった。 そこでこれと似たようなものをユニクロで探したら、なんと3280円で買える。 世の中にはただの木綿のショートパンツを、16万円も出して買う人がいるのに驚いた。 次回になにかイベントがあるかもしれないと思い、LINEを削除出来ないでいる私だ。 【HARUMI FLAGの中国人(1)】 我が家の近くの2021東京オリンピックの選手村は、現在は分譲住宅となっている。 ここは東京オリンピック後に東京都から民間不動産会社へ売却されたが、近隣の相場より相当安かった。それでも不動産会社は、これだけ多くの物件を完売できるか不安になり、購入申し込みに条件を付けなかった。 そのために中国人が大量の申し込みをして、本当に必要な一般日本人購入者が抽選で外れてしまった。これが最近になり「違法民泊」に発展し大きな問題となり、住民とのいざこざを起こしているそうだ。 夜中に大騒ぎする。ゴミの分別はしない。足湯でおむつを洗う。部屋で中華料理店を開いている者もいるらしい。エレベーターホールには大きく「民泊禁止」の貼り紙があるが、中国人に無視されている。 【HARUMI FLAGの中国人(2)】 最近であるが住民が国会議員に訴えたことで、「晴海フラッグ」の「違法民泊問題」が国会で取り上げられた。ここには1万人が住んでいることになっているが、その内の2000人に居住実態が無いようだ。 さらに実際に住んでいる8000人の内の1000人が、外国人(中国人?)のようである。 日本に住んでいない中国人が投資目的で購入し、しかも中国人相手に違法の民泊事業をしているようだ。宿泊予約と支払いはネットで中国で済ませているので、日本にお金は落ちないので税金も取れない。 国会の政府答弁では「シッカリ調査をして、対応する」とのことだが、所有者の3分の1が外国人となると、管理組合の総会決議にも問題が出そうだし、将来ここが中国人村になることが心配される。既に嫌気がさして、ここを売却して出て行った住民もいるようだ。 【釣り人】 私の住むマンションの裏に接して、朝潮運河がある。 運河には「朝潮小橋」という橋が架かっていて、晴海フラッグや晴海ふ頭公園に行ける。この運河で時々、見掛けるが釣り人がいる。何が釣れるのかは聞いたことが無いので、分からない。海からここまで300メートルくらいの距離なので、水は海水で海の魚が釣れる。 以前の私の地元から海に行こうとすれば、車で2時間くらいは掛かる。 それがわずか数分で海釣りが出来るのだからありがたいのだが、残念ながら私には釣りの趣味が無い。 【廃業するパチンコ屋】 銀座4丁目から築地方面に少し戻った昭和通りの角に、数年前まで向かい合ってパチンコ屋があった。それが相次いで廃業し、片方は「薬局チェーン店」、もう一方は「時間貸し駐車場」になっている。 パチンコは最盛期には遊戯人口が3000万人いたが、それが現在は800万人となっている。衰退の理由は色々あるが、「新台入れ替えサイクルが早過ぎる」、「出玉規制が厳しくなった」、「若者はパチンコをやらない」などのようだ。私はもともとパチンコのような賭け事はしないので、何が面白いのか分からない。 それより駐車場の隣り角の「大野屋」が気になる。この店は1927年の町屋建築で、和装小物の専門店らしい。2~3年前には店は開いていたが、最近は閉めたままだ。 時代に付いて行けない2業種のようだ。 (おまけの話)【領土主権展示館】 中央区の区報に「講演映画と映画の集い」の案内が出ていた。 詳しく読んでみたら、女性落語家の「三遊亭律歌」の講演と、映画「老後の資金がありません!」だった。 いつもは申し込みは不要なのでそのつもりでいて、前日に開催場所の確認をもう一度したら、サイトを開いたら「申し込みは終了しました」と出ていた。「えー!」と驚いたが、区報を良く見なかった私に問題があるのだが、とても残念だった。 そうなると行くところが無くなってしまった。仕方ないので以前になにかで見た覚えのある、虎ノ門にある「領土主権展示館」がリニューアルしたようなのでそちらに行った。 どうも最近はボケ話が多過ぎる。 東京BRTに乗って「虎ノ門ヒルズ」で降り、暑い中を「領土主権展示館」まで10分くらい歩いた。この施設は資料によると外務省の管轄で、『北方領土・竹島及び尖閣列島が我が国固有の領土であることを示す歴史的資料や人々の営みを示す資料をまとめて紹介する初めての国の施設です』とある。 今年の4月にリニューアルされたそうだが、私は日比谷公会堂の下にあった時も、虎ノ門に移った時も見に行っている。 館内に入ると、先ず涼しいのが嬉しい。係の女性が親切に見学順路を示してくれる。 展示は「北方領土」、「竹島」、「尖閣諸島」がそれぞれの大きなパネルで、歴史的な日本の主権に付いて古い写真などと共に紹介している。これを見ると、ロシア、韓国、中国の歴史捏造がよく分かる。 館内は写真撮影はOKなので、自撮り写真も撮った。 リニューアル前は無かった展示に、タブレットと大画面の動画映像があった。 階段を少し上がった約35~40平米の特別室に入ると、左右・上下・前面の5面に一体化した映像が流れる。自分の足元にも映像が流れる。これはとても良い。お勧めである。 尖閣諸島の外からと、北方領土・竹島の海の中の自然を映し出す。北方領土と竹島はロシアと韓国が不法占領しているので、映像は海の中だけなのが残念だ。 見終って出口に行ったら、タブレットによるアンケートを依頼された。全てを「最高」にチェックした。 帰りに記念に「領土主権展示館」の文字入りのボールペンをもらった。
心の伊達市民 第一号

0
1
-

2025/07/10(木) - 観光・体験
- NEW
小さな話(28)
【我慢の70分】 35度の気温で暑くて行く予定が無かったので、宝町の「宝くじドリーム館」にイベントを見に行った。この日はランチタイム・クラシック・コンサートをやっていた。 出演は廣田美穂(ソプラノ)、中井亮一(テノール)の競演で、100人くらいの観客が来ていた。 私はどうもオペラは苦手で、イタリア語で歌うので、なにがなんだか分からない。 それに特にソプラノは脳天を突き抜けるような高音が、私には耐え難い。 通常は50分くらいのイベントが、この日はアンコールを含めて70分にも及んだ。 来ている人達は老人ばかりで、オペラが好きとも思えない。ただ涼みに来ていたのでは? 【築地市場の外国人】 都バスで銀座方面に出る時は、築地場外市場の横を通る。 市場には多くの外国人観光客が、何が面白いのか暑い中を見物に来ている。 どこの国でも、市場はその国の庶民の生活が分かり面白い。 でも築地市場は専門業者はほとんど豊洲に移ってしまい、今では観光地になってしまった。飲食店や買い食い店ばかりになってしまい、庶民の台所ではなくなった。 暑い日が続くので、若い外国人女性は下着のような格好で歩いている。 イスラム教徒も来ているが、目の毒ではないだろうか? 【今日から一句】 毎週木曜日の午後7時から、6チャンネルで「プレバト」という番組がある。 その中のコーナーで「俳句」があり、「夏井いつき」という口の悪い先生が登場する。 私は以前に「かに道楽」と「おーい、お茶」の俳句募集に応募したことがあるが、入選にはほど遠かった。 最近になり図書館から夏井いつきの「今日から一句」という本を借りて来て、少し勉強しようと思った。俳句を初任者向けに易しく解説している本だが、「そうかー!」と勉強になった。参考になったのが「映像を切り取る」と、「季語+季語と関係ない12音」であった。 そこで私も一句。 『炎昼の 買い食いだらけ ツーリズム』 (暑い中を外国人観光客が買い食いをしている様子) 【もうこの季節】 銀座4丁目のバス停近くの小公園の前を通ったら、もうミスト噴射を始めていた。 例年なら7月の半ば過ぎないと始まらないと思っていたが、今年は早く始めたようだ。 東京の「梅雨入り宣言」が出されたら、それをキッカケのように高温の日が続いている。 地球温暖化が言われて久しいが、梅雨が無くなったような気候は温暖化に関係があるのだろうか? ミスト噴射は見ているだけで、涼しげである。 その下に行くとミストを浴びて一瞬は涼しくなるが、そこを離れると元の木阿弥である。 【なにを並んでるの?】 銀座4丁目のバス停の近くに、いつも外国人が並んでいる場所がある。 その前に行ったが、店は無くエレベーターを待っている人達だった。 ビルのフロアの看板を見ると、どうも7階の「幸せのパンケーキ」以外になさそうだった。 『なぜこんなところに並んでいるの?』とも聞き難いので、家に帰ってから調べてみた。この店は創業は2015年で、表参道店が第一号のようだ。全国に23店舗もあるのに知らなかった。メニューを見たらスタンダードのパンケーキは1380円、飲み物が350円で、両方で1730円はかなり高い。 行ってみたい気もするが、外国人に混じって並んでまでは食べたくない。 【2両連結BRT】 東京BRTが運行を始めた頃は乗客も少なく、「これで採算がとれるのだろうか?」と心配した。ところが最近は利用者が増えて、座れない時さえある。 「汐留」から帰る時に、たまに「晴海5丁目」、別名(HARUMI FLAG)行きに乗ることがある。これに乗ると私の住むマンションの裏側に停留所があるので、少し歩くが運河沿いで気持ちが良い。 停留所で降りたら、向かい側に2両連結のバスが見えた。 近付いてみたら、後部のガラスに「全長18m追い越し注意」と書いてあった。 車体重量は約12トンのようで、ガソリン車であった。保有台数が少ないので、滅多に乗ることはない。 (おまけの話)【同級生交歓】 段々と古くからの友人が亡くなったり、パソコンを止めたりして交流が減って来るのは仕方ないことだ。だから残っている友人は大切にしようと思い、毎月1回、中高時代の同級生と「都心を歩かない会」を開催して来た。 今回は新橋駅集合で、東京BRTに乗って東京ビッグサイトへ行ってランチの企画となった。 東京BRTの新橋停留所に行ったらなぜか臨時便で大勢の中年女性が列を作って並んでいる。腕章を付けた係の男性が案内をしている。 私は彼に聞いてみた。『これは何の団体ですか?』。 男性は面倒くさそうに『色々やっている会です』と言った。 家に帰ってからネットで調べたら、「三菱UFJ銀行」が主体となり147社が参加して、保険・人材派遣などをやっているグループの顧客の会のようだった。この日は会員向けにバーゲンセールを有明GIM-EXで開催するようで、みんな途中で降りて行った。 東京BRTの終点の「国際展示場」で降りて、すぐにランチ会場の「COCOS」に向かった。この店は席でタブレットで注文をすると、配膳ロボットが料理を運んで来る仕掛けになっている。ところが珍しいミスが発生し、ロボットが私たちが注文していない料理を運んで来た。 食後は東京ビッグサイトを背景にみんなで記念撮影してから、館内に入りカフェでお茶の予定だった。しかしものすごく広いカフェには空席が無く、仕方ないので帰ることにした。 1階の広い都バスの停留所に行って、「東京駅丸の内南口」行きのバスを待つ。 しばらくしてやって来た都バスは、乗る人も少なくガラガラだった。 バスが「新豊洲駅前」に到着したら、予想通りに大勢の外国人観光客が乗り込んで来た。彼らは外国人に人気の「チームラボ」に行った帰りなのである。 バスはギュウギュウ詰めでもう乗れないので、途中のバス停では乗車口を開けなくなった。私は途中の「勝どき駅前」で降りたが、混み過ぎていてみんなに挨拶も出来なかった。この路線を利用する時は、いつも「オーバーツーリズム」を体験している。
心の伊達市民 第一号

0
2
-

心の伊達市民 第一号

0
1
-

心の伊達市民 第一号

0
3
-

心の伊達市民 第一号

0
1
-

ホテルマンの幸せ

0
-

心の伊達市民 第一号

0
3
-

心の伊達市民 第一号

0
2
-

ホテルマンの幸せ

0
-

心の伊達市民 第一号

0
2
-

心の伊達市民 第一号

0
2
-

心の伊達市民 第一号

0
2
-

心の伊達市民 第一号

0
1
-

心の伊達市民 第一号

0
1
-

ホテルマンの幸せ

0
-

心の伊達市民 第一号

0
2
-

心の伊達市民 第一号

0
1
-

心の伊達市民 第一号

0
1
-

ホテルマンの幸せ

0
-

心の伊達市民 第一号

0
1
-

心の伊達市民 第一号

0
2
-

心の伊達市民 第一号

0
2
-

心の伊達市民 第一号

0
2
-

心の伊達市民 第一号

0
1
-

-

心の伊達市民 第一号

0
2
-

心の伊達市民 第一号

0
2
-

心の伊達市民 第一号

0
2
-

心の伊達市民 第一号

0
1
-

心の伊達市民 第一号

0
2
-

心の伊達市民 第一号

0
2
-

心の伊達市民 第一号

0
2
-

心の伊達市民 第一号

0
2
-

心の伊達市民 第一号

0
2
-

心の伊達市民 第一号

0
2
-

ホテルマンの幸せ

0
-

心の伊達市民 第一号

0
1
-

心の伊達市民 第一号

0
1
-

ホテルマンの幸せ

0
-

心の伊達市民 第一号

0
2
-

心の伊達市民 第一号

0
2
-

心の伊達市民 第一号

0
2
-

心の伊達市民 第一号

0
2
-

心の伊達市民 第一号

0
2
-

心の伊達市民 第一号

0
1
-

心の伊達市民 第一号

0
1
-

心の伊達市民 第一号

0
1
-

心の伊達市民 第一号

0
1
-

心の伊達市民 第一号

0
2
-

心の伊達市民 第一号

0
2
-

ホテルマンの幸せ

0
-

心の伊達市民 第一号

0
1
-

心の伊達市民 第一号

0
1
-

心の伊達市民 第一号

0
1
-

心の伊達市民 第一号

0
2
-

心の伊達市民 第一号

0
2
-

心の伊達市民 第一号

0
2
-

心の伊達市民 第一号

0
1
-

心の伊達市民 第一号

0
2
-

心の伊達市民 第一号

0
2
ハッシュタグ
- 海外の話題(16件)
- 絵画教室(16件)
- COCORO(14件)
- モンゴル旅行(12件)
- 伊達市(11件)
- 水彩(9件)
- 油彩(8件)
- 浮腫み 余分な水分 (7件)
- 気血水(6件)
- 夏(6件)
- 夏バテ 汗 (6件)
- 気の流れ(6件)
- 薬膳 肝 気血(5件)
- 潤す 免疫力(5件)
- 薬膳 食材 教室(5件)
- 寒邪(4件)
- PCデザイン(4件)
- 免疫力 潤い(4件)
- 春(4件)
- 冬(4件)
- 梅雨時期(4件)
- 気の巡り 温性 陳皮(4件)
- 二十四節気(3件)
- 介護 セミナー 社会福祉協議会(3件)
- 腎(3件)
- 薬膳 カレー スパイス 気の巡り(3件)
- デッサン(3件)
- 薬膳 教室 参加 〆切(3件)
- 薬膳 教室 気血 毒出し(3件)
- 秋 乾燥 躁邪 肺 腸 潤す(3件)
- 寒い(2件)
- 脾 湿 鬱(2件)
- 脾胃(2件)
- シュトーレン クリスマス(2件)
- 体験(2件)
- 雑穀米(2件)
- 薬膳 気虚 血虚 温性 胃腸(2件)
- 潤す 肺(2件)
- 白い食材(2件)
- 友人たち(2件)
月別アーカイブ
観光・体験 人気の記事
-

07/03(木) 幸せな人生の大きな要因
-

07/07(月) 写真で見る東京(112)・・・月島もんじゃ通り
-

07/08(火) 写真で見る東京(113)・・・・兜町を探索
-

06/30(月) 果てしなく遠い甲子園への道
-

07/05(土) 天の川イルミネーション
-

02/20(木) 私の方が『KEY TO LIT』
-

02/17(月) 小さな旅(8)・・・「べらぼう」の街
-

04/30(水) 小さな話発見(38)・・・九段から東京駅
スポンサーリンク
-

06/25(土) - 広告
四季を通じ、「外」とつながる暮らしの提案
ダイニングに向かう動線の視線の先にも、光の漏れる地窓。
イベント
「観光・体験」カテゴリーのおすすめ記事
-
心の伊達市民 第一号

0
2
-

2025/02/10(月) 今日と明日は連休です!!
-

2025/05/16(金) 竹内さんファン必見!!
ホテルマンの幸せ

0
-

2025/02/20(木) 私の方が『KEY TO LIT』
ホテルマンの幸せ

0
-
ホテルマンの幸せ

0
観光・体験に関する
特集記事
-

『染まらないために染める』パンチラインな大和魂 〜異端児染師Aizome『I』
作務衣を纏った渋めの男性が現れると思いきや、目の前の染師は2パートに刈り上げたヘアスタイルの、抱いていたイメージとは程遠い方でした。 そのカッコいい雰囲気に釘付けになったところから取材は始まりました。 人生、何がきっかけで何が起こるかわからない。 金子夫妻と話をしているとつくづくそう思います。 「藍と出会って人生が変わった。」 今回お話しを伺ったのは、そうきっぱりと言い切る金子智志さんと愛さんです。 本当にこんなところに工房があるのだろうか…? 地図を頼りに探し当てた工房のある土地を見て驚きました。 湿地と田んぼに囲まれた広大な土地。 そこには、小屋を含め廃屋が何軒も建っていました。 「え!? こんな場所があったんだ!!」 それが筆者の第一声。 けれども同時に思ったこと。 それは〜。 「このお二人はなんて大きな夢を抱えているんだろう!」 ということ。 どんなに広い土地が欲しくても、この状況を見たら恐らくは誰もが諦めるだろうと思います。 なによりも廃屋の数が多いので壊すのが大変。 構築物も多い庭は広すぎて手入れも大変です。 ここを買うのは、たくさんお金を持っている人か、夢が大きく手入れが苦ではない人だと思いました。 現れたご夫婦と出会い、一目でこのお二人は後者だと直感しました。 ヒップホッパーが染師になると決めた日 金子愛さんは、伊達紋別駅近く「クリーニングのかねこ屋」の娘として生まれ、ピアノ教師を生業にされて今年で21年目。 その愛さんがパートナーとして選んだのは、ヒップホップに勤しみMCを生業にすることを志していた智志さんでした。 出会ったのは、その智志さんが夢をあきらめ、故郷の伊達市にUターンし、その後しばらくした頃のことでした。 「12年前、札幌から帰ってきてからは建築業に就いていました。」 そう話す智志さんの口から出てくる言葉は、とにかくイチイチ面白い! 韻を踏むような言葉がポンポンと出て来ます。 さすが、MCを目指していた方! 「僕、言葉が大好きだし大切にしているんです。ヒップホップをやっていたので、韻を踏む言葉の並びで、複雑な心の動きや物事の状況をバシッと表現するのが好き。そういうのパンチラインて言うんですよ。でもね、『言葉より藍!』と確信する出会いがあったんです。 藍に出会ったのは6年前でした。ニューヨークで寿司屋をやっている友達と会ったのですが、彼はアメリカに住みながら、日本人としての紺色にこだわりを持っていました。『和の心』を紺色=ジャパンブルーに求めていたのです。その時、僕の中に何か響くものを感じました。その日から、頭の中が紺色でいっぱいになりました。黎明館(藍の体験館)に通ったり、独学で学んだりしてすっかりと『藍』にハマってしまったんです。」 へ〜! パンチライン! 初めて耳にする言葉です。 最初は少々緊張していたお顔の智志さんでしたが、徐々に頬を緩め、次々とパンチラインをちりばめて語り始めました。 「とにかく藍染にハマって、3年間独学で染めていました。でもどうしても独学には限界がありました。そこで3年前、徳島の『BUAISOU』の研修生に応募しました。全国でわずか3名の狭き門に合格して研修生になることができ、12日間の研修をさせていただきました。そして、どうしても迷いがぬぐえず自信が持てなかった僕のやり方を『それでいい』とお墨付きをいただくことができたんです。嬉しかった。ようやくこのまま突き進んでいいんだ!と自信が持つことができました。」 『BUAISOU』について 世界各国からワークショップの依頼が殺到し、ハイブランドとコラボし、グローバルな活動をし続ける徳島の藍染工房です。 徳島県を拠点に、藍の栽培から染色、仕上げまですべてを一貫して行うBUAISOUは、古き良き伝統をそのまま受け継ぐのではなく、常に進化をし、先人たちをリスペクトしながらもそれを超えていく努力を続け、未来に繋ごうとしている。 わずか5人で運営する工房は、2015年4月されました。BUAISOUの名は、白洲次郎の邸宅「武相荘(ぶあいそう)」にちなんだものだそうです。 Bluem の誕生 ところで智志さん、『BUAISOU』研修においてお墨付きを得られたものの、しばらくは染師と建築の仕事の草鞋を二足履いていました。 けれども次第に口コミでオーダーが入る様になり、二足の草鞋を履いていては藍染の仕事が追いつかない状況になりました。 技術の確かさも証明されました。 それは「伊達美術協会」から表彰された『協会賞』という最高賞。 月と海、人間と自然を表した作品。 タイトルは『183672144288』 タイトルの意味はこうでした。 〜人と月と海の共通となる数字『18』。その18の倍数が人間の『生』を表し、目には映らない人と自然のつながりを人類が最も信頼し、裏切られてきた『数字』で表現しました〜 18:1分間に月が引き起こす波の回数=人間の1分間の呼吸の回数 36:人間の平均体温 72:人間の1分間の心拍数 144:人間の最高血圧 288:日数に変えると10月10日で妊娠期間と同じ 「人間が最も信頼し、裏切られてきた数字」この言葉だけで俄然実物を観てみたくなりました。 6月3日より2ヶ月間、「だて歴史文化ミュージアム」において展示会が開催されます。 「本格的に染師として生きていきたいと考えていたので、そのためにも自分の工房が欲しい!と思っていました。工房にする場所をずいぶん探したのですが、タイミングや予算も含め中々『ここだ!』という所に出会えなくて…。 がっくり‥としかけた一昨年の冬、出会ったのがこの場所でした。見に来たら一目惚れ。だいぶ荒れていましたが迷いはありませんでした。実はここ、子どもの友達のおばあちゃんの家だったところなのです。妻がそれを思い出してくれ、購入に結びつきました。」 昨年6月、ついに念願の城が手に入りました。 金子さんご夫婦にとっては夢に向かうThe 1’st stage『Bluem』です。 “ Blue “ × “ Bloom “ つまり青=藍 と開花。 藍で笑顔の花を咲かせたい! 藍で自分たちも開花したい! そんな想いが込められていました。 韻を踏む言葉が大好きな智志さんらしいネーミングです。 「『Bluem』は『藍』製品をカッコいいものとしてブランディングしていく場だと考えています。異文化交流はもちろん大事です。でも日本人として異文化を受け入れながらも、大和魂というか、『和の心』を『藍』を通して表現したい。だから『染まらないために染める』んです。ここを『まちのハブ』として育てて、いろんな人たちと繋がりながら行動して、自然を尊ぶ日本人のDNAを呼び覚ましたいんです。」 循環型ファッションを目指して ところで、今までの経済合理性は短期的にも長期的にも継続は難しい状況だと言われています。 そんな中、若い人を中心に高まってきたのが「気に入ったものを修理したり、染め直したりして長く使いたい」というニーズ。 衣料メーカー自体が「お客様に頻繁に買い替えさせる売り方ではなく、アフターケアを軸に『3つのR』をビジネスモデルの根幹にしていると言われています。 R:リユース(再利用) R:リデュース(使う資源を減らす) R:リサイクル(再資源化) の3つです。 「僕は自然のこと全然詳しくないです。SDGsとかもよくわからない。まあ持続可能な社会を目指そうということですよね。でも思うんですよ。藍もそうですが、人間は自然の恩恵なしには生きていけない。食べ物だってなんだって素材は全て自然が与えてくれています。でも、人間の勝手で飽きたり汚れたりすると簡単に捨てられてしまう。元は全て命なのに。そんな傷んでしまったり、汚れてしまったりしてしまったものを藍染によって甦らせることができるんです。幸い妻の実家がクリーニング屋なので、汚れやシミはしっかりと取り除いてから、新たな命を吹き込むことができる。おまけに堅牢性も増します。モノを大切に残すためのお手伝いができるのも幸せを感じることです。そうそう!あるピザ屋さんの窯から出た灰も藍染めに使えるんですよ。灰だって元は木。いただいた命に感謝して、最後までできるだけ捨てず使わせていただきたいと思っています。子どもたちの子ども、もっと未来の子どもたちのためにヒトが生きる源の自然を、僕らの役目として僕らの仕事で残して行きたいです。そう、『サスティナブルー』な仕事として。」 最後は韻を踏んで締めてくれました。 智志さんの中では当たり前の活動から生まれる循環。 ヒトもモノも自然もとても大切にされているお人柄が窺えるお話しでした。 人との出会いを一つ一つ丁寧に心に刻んでいるからこそ繋がっていく糸。 きっとお二人の出会いも…♡ 何度かその話を振りましたが、どうやらお二人だけのシークレットのようです ^^ お話しをしていて感じたのですが、ご夫婦のお人柄が多くの素敵なご縁の糸を手繰り寄せている気がしてなりません。 それを証明するかのようなイベントが、昨年の夏に開催された初イベント「草紙奏藍」でした。 先の見えないコロナ禍真っ只中、子どもも大人もみんなが疲弊してどんどん笑顔が少なくなっていく状況に、心を痛めていた金子さんご夫婦が立ち上がり開催されたのが、この『草紙奏藍』でした。 結果大盛況でしたが…。 思いついたのはいいけれど、正直他の作業もあり気持ちはいっぱいいっぱい。 広すぎる庭の草刈りはおろか、イベントに際しての環境整備もままならない。 途方に暮れそうになった時、助けてくれたのは、金子夫妻の活動を見守ってきた地域の方々や友人たちでした。 中には遠方から駆けつけてくださる方もいました。 畑違いの仕事から飛び込んだ『藍』の世界でしたが、元々のお二人の仕事や趣味の人脈のおかげで、予想を遥かに超えるお客様にお越しいただき、イベントは大盛況のうちに終わることができました。 もちろん、評判は上々。 きっと、今年の夏も期待されているのではないかと思います。 「今後もイベントは色々開催していきたいと考えています。全国シェア2位と呼ばれる篠原さんの藍の生産と“すくも”に加えて、染師としての技術や製品もグローバルに羽ばたかせて行きたいです。まずは「藍の町」伊達を歩く人たちの服や小物を藍色に染めたい!と思っています。」 2時間に渡った取材は、お話し上手な智志さんに乗せられ、素敵すぎる愛さんの笑顔に乗せられ、楽しくて楽しくてあっという間でした。 その楽しさはきっと、お二人に関わった方皆様が感じることだと思います。 I (藍)の形をバトンになぞり。 I (私)が染師として。 大和魂のI (愛)を届ける。 きっと、最後の『愛』は妻の愛さんと共に〜の意味が込められていることと思います。 AIZOME「I」 / Bluem 情報
Rietty

0
-

-

景色がごちそう☆ “ モントーヤ “ ですごす ゆったり時間
温泉街から国道230号線を車で走ると、洞爺湖の上、畑の真ん中に突如現れる黒いコンテナ。 直線道路なので、気になりながらも通り過ぎ、農機具の倉庫かな?一体なんだろう?と気に留めていた昨年。 そんな、筆者のような読者の方もきっといらっしゃったことと思います。 そして今年、どうやらOPENしたらしい!との情報を得て、謎を解くべく取材をさせていただきました。 ↑この束石がポツネンとあるだけの国道からの入り口 ちょっぴり勇気がいる入り口からコンテナを目指して奥へ向かうと、そこには遮るものがほとんどない空間。 畑だと思っていたこの土地は、実は畑ではありませんでした。 周りを見渡して感動しました。 ぐるっと300度くらい見渡せます。 しかも、羊蹄山・尻別岳・ニセコ連邦・昆布岳・有珠山などなどが一望でした。 尻別岳 羊蹄山 取材に訪れたことをうっかりと忘れ、うっとりとゆったりモードにスイッチが入りそうになってしまったほどの眺望です。 「危ない 危ない」と、気を取り直して玄関に向かうと、思わず開けたくなる可愛らしい赤いドアがありました。 ↑入り口にメニューがあるのは安心します ↑ドアを開けると可愛いくて不思議でユニークなディスプレイ ↑厨房で忙しそうないずみさん こちらは、2022年5月にオープンしたカフェ&キャンプサイト “ モントーヤ “です。 札幌から6年前に移住して来られた オーナー 井上啓二さんと奥様 いずみさんが営むお店です。 実はお会いして驚いたことがありました。 ご縁というのは不思議なものだとも思いました。 ↑大きな窓からは遠くの山がよく見えます 奥様のいずみさんは2年前、筆者が企画したワークショップに参加してくださった4名様のうちのお一人だということ。 オーナーの啓二さんは、筆者がどうにも気になって気になって、何度も探しに行った洞爺湖畔の幻の珈琲ソフトクリーム屋さんのオーナーさんだったということ(数ヶ月で満足して閉店)。 そうだったんだ! そうだったんだ! このような形でお会いできるとは! と、敷地に入った最初から少々興奮気味の筆者…^^; 店内は、外からは想像できないくらい落ち着いていて、どこか懐かしい雰囲気の調度品が並んでいます。 ジャズが心地よく流れ、レコードジャケットやコレクションの古いカメラが並びます。 ↑筆者好みのアーティストとレコードジャケット ↑昭和感漂うレトロなコーナー。 「東京に居た頃は服飾デザインの仕事をしていました。いわゆるDCブランドの服です。札幌に戻ってからは、もともと好きだった馬の仕事に携わりました。馬の競りのためのプロモーションビデオを制作したり、牧場のWebを制作したりする仕事です。札幌競馬があるときは、競馬場で売店も営みます。だからまあ、そちらの仕事が本業かな。」 ↑こちらはオーナーの本業。代表取締役としての会社「inox」のwebページ なるほど…。 馬に関わる映像のお仕事と“ モントーヤ “の関連がいまひとつ見えませんでしたが、飲食業にはすでに携わっていらっしゃったわけです。 そして、奥様とのご縁も馬が取り持ったとか♡ ↑コンテナは雨よけにもなり、イベントなどのショップにもご利用いただけます。 1本だけ残したドロノキ(ヤマナラシかも)は、シンボルツリーになっています 「この5000平米の土地は、僕が買う前は何十年も手付かずだったそうです。太くなった木も草も伸び放題のジャングル状態。崩れ落ちた家もそのままで荒れ放題。呆然としてしまうような荒地となっていました。水道も通っていませんでしたので、大掛かりな工事になりました。途方に暮れるほどの手間を掛け、足掛け4年がかりで開墾していきました。」 「そこまで苦労して…。この場所の何にそんなに惹かれたのですか?」 「景色です。どこを見ても山があるこの景色を見ながら珈琲が飲みたかった。ただそれだけです。」 それまで、クールな面持ちで話をされていたオーナーの目が、ふっと力が抜けて優しくなった瞬間でした。 この景色を見ながら一杯の珈琲(お店の珈琲は札幌の有名焙煎ショップ「斉藤珈琲」の豆使用)が飲みたいというそれだけで、4年間も開墾をしてしまう井上夫妻がなんとも素敵です。 「でも、そもそも何故札幌から移住して来られたのですか?」 「きっかけはスイスを訪れたことでした。もう本当にスイスが素晴らし過ぎて、人生観が変わりました。ほんと、絶対に行ったほうがいい!」 この時のオーナーの目はキラキラに輝いていました。 そのご様子だけで、どれほどスイスが素晴らしかったのかが分かりました。 「帰国後、札幌に住まなくても今の仕事はできるよね?と夫婦で話すようになりました。その時の場所の候補は、北海道の都会ではない景色の良いところ、もしくは南阿蘇でした。 そうして洞爺湖畔に居場所を見つけ、その2年後、周りの山々が見渡せるこの場所が気に入り購入しました。」 それから、足掛け4年の開墾の日々が始まったのでした。 店舗は、コンテナ7つを繋げて造られています。 大きな窓の店内はオーナー自らがデザインされたもので、お気に入りの調度品は、山を楽しむためのレイアウトになっています。 「ところでメニューを見せていただけますか?」 とお願いし、見せていただいたのがこちら。なんと、絵本でした。可愛い〜♡ ↑画像はありませんが、珈琲おいしくチーズケーキが絶品です! ↑次回はこちらを食べてみたい! ↑生パスタも美味しそう〜♡ そういえば、入り口にも店内にも絵本が飾られていました。 てっきり、いずみさんのご趣味かと思いきや…。 なんと、「僕のアイディアです」と。 この時のオーナーはちょっとハニかんだ笑顔でした。 ↑思い切り照れたお顔で振り返ってくださったショット ところで、“ モントーヤ “ の “モン“ とは、フランス語で “私の”という意味だそうです。 つまり” 私の洞爺”。 それでも湖畔ではなく、300度にわたり遠くに山を望めるここを選んだのは、「ここで珈琲が飲みたかったから」。 ここがオーナーにとっての「私の洞爺」なのですね。 「洞爺湖も有珠山もいい。でも、ここから眺める羊蹄山も洞爺湖町のランドマークであって欲しいのです。阻害するものが何もない畑のど真ん中で、この景色を楽しみに来ていただきたいです。」 ↑キャンプサイトご利用の場合は店舗の玄関フード内のトイレが共用利用できます 今後は、プライベートキャンプサイトも整備して行くそうです。 ただし、利用できるのはオーナーの友達か、友達の紹介限定だそうです。 優しく尖った カフェ&キャンプサイト“ モントーヤ “。 広大な土地にポツンとコンテナは目立ちますが、素敵な隠れ家を見つけました。 ―モントーヤ情報―虻田郡洞爺湖町成香19営業日時はInstagramまたはHPをご確認ください。Instagramhttps://instagram.com/montoya_108?igshid=YmMyMTA2M2Y=HPhttp://montoya.jp/*イベントのご利用も可能です。HPのお問合せフォームよりご相談ください。
Rietty

0
-